エイジングケア商品として、ヘアケアブランドの「LPLP(ルプルプ)」シリーズとスキンケアブランドの「NINE SENSE PHYTOLIFT(ナインセンス フィトリフト)」シリーズを展開するスタージュ株式会社。別のカートシステムからecforceに移行後、2つのブランドサイトを統合してどのようにEC運営を行ってきたのか。また、ecforce maやecforce biの導入における活用方法や業務効率化について、同社情報戦略部 課長補佐の米増充氏と、同社オンラインセールス・コミュニケーション部 セールス業務推進チーム 課長の植田佳代子氏にお話を伺いました。
エイジングケア商品を手がけるスタージュ
ー御社の事業内容とブランドの成り立ちについて教えてください。
米増 充氏(以下、敬称略):スタージュは2014年に設立された会社で、主に化粧品の企画と製造販売を手がけています。エイジングケア商品として、ヘアケアブランドの「LPLP」シリーズとスキンケアブランドの「NINE SENSE PHYTOLIFT」シリーズを展開しています。
LPLPシリーズは、海藻由来の成分とバイオテクノロジーを融合させたシャンプーやトリートメント、白髪ケアのカラートリートメント、薬用育毛エッセンスといった商品を展開しています。 NINE SENSE PHYTOLIFTシリーズは、植物由来の成分と最新テクノロジーを融合させたスキンケアブランドで、オールインワンジェルやスキンクリアローション、クレンジングジェルといった商品を展開しています。LPLPが50代を中心として40代から60代、NINE SENSE PHYTOLIFTが40代を中心として30代から50代の女性をターゲットとしています。


植田 佳代子氏(以下、敬称略):もともと親会社が衣料品のカタログ販売を手がけていて、同様の年齢層の女性をターゲットとしていました。そこから派生してヘアケアブランドのLPLPとスキンケアブランドのNINE SENSE PHYTOLIFTが立ち上がりました。
商品自体は、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングといったモールでのオンライン販売や一部店舗でも取り扱いがありますが、基本的には自社ECサイト「STELLA SENSE(ステラセンス)」(https://www.stellasense.jp/)がメインの販売チャネルです。定期的に百貨店のポップアップストアでオフライン販売を行うこともありますが、8割〜9割ほどがオンライン販売と、比重が大きいですね。
操作性の改善と2ブランドのサイト統合を目指してecforceを導入
ー以前のECシステムにはどのような課題があったのでしょうか。
米増:以前利用していたのはパッケージ型のECシステムでした。その前がスクラッチのシステムだったこともあり、パッケージ標準の機能だけでは足りず、多くのカスタマイズを行っていました。しかし、標準で連携している外部サービスがあまりなく、何か新しい施策をやりたいとなった場合には追加のカスタマイズが必要になり、時間もコストもかかるという状況でした。また、ブランドごとにECシステムが別々だったため、運用面においても不便なところがあり、新しいECシステムへの切り替えの話が浮上しました。
ーその中でecforceに決めた理由を教えてください。
米増:他社のECシステムも検討しながらでしたが、さまざまなECシステムのサービスがある中で、ecforceは非常に勢いがあり、伸びているサービスという印象がありました。日々アップデートがなされているプロダクトということで魅力的でしたね。また、EC運営における課題となっていた2つのブランドのサイトを統合管理しながら運用できることも、ecforceに決めた理由の一つです。
2024年6月にサイトリニューアルを行い、ecforceで運用を開始しました。当初はいろいろばたつくこともありましたが、運用が安定したのは秋ぐらいでしたね。


ecforceの導入でこれまで実現できていなかった新たな施策を開始
ーecforceを導入して、どのような施策を行っていますか。
米増:ecforceは連携できる機能が多いので、移行したタイミングで会員ランク制度やポイント制度に取り組んでいます。まずはLINEのID連携をしてくださったお客様を対象としたポイント制度を開始しました。直近では期間限定のポイントアップキャンペーンを実施したり、バースデーポイントの付与も開始したりしています。
以前のシステムでも、LINEのID連携はカスタマイズすれば可能ではありましたが、外注する必要があったので時間とコストの面で断念していました。ecforceはEC運営に必要な機能がデフォルトで搭載されているので、私たちのやりたいことをカスタマイズなしで実現できるところがいいですね。また、分断していた2つのブランドのECシステムを一つに統合できたので、運営コストの削減にもつながっています。
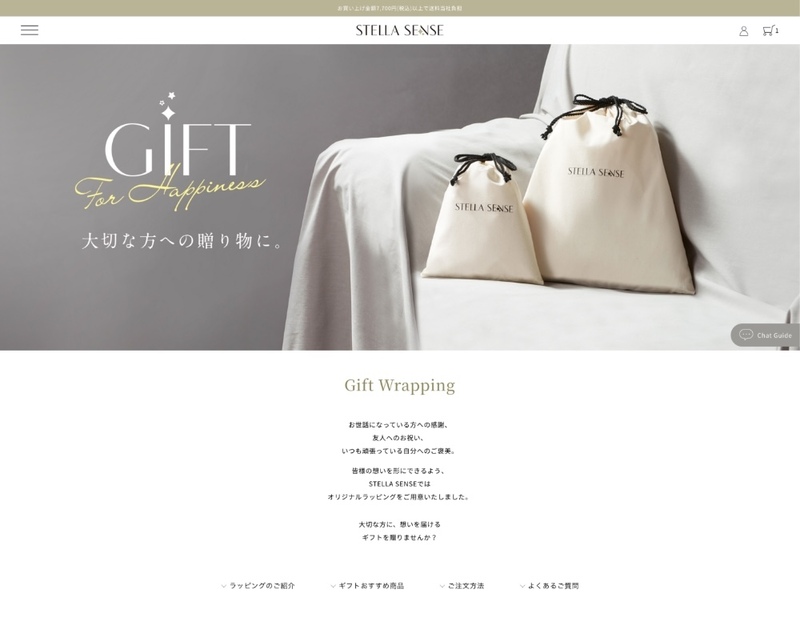
まだ試験的ではありますが、ギフト購入の対応やお友達紹介ポイントの付与といった施策、ecforce chat*の本格的な運用も視野に入れ動かしていきたいです。
*ecforce chat:ウェブ接客自動化システム。問い合わせに対して適切な応対から提案まで自動化し、顧客LTVの向上やオペレーションコストの削減をサポートする。
ーecforceの導入で改善された点があったら教えてください。
植田:これまで定期サイクルの変更のお問い合わせなどは、お電話でいただくケースがほとんどでした。ecforceを導入してLINE連携を実装してからは、各種変更をLINEから行なっていただけていることがわかりました。お客さまからしたら、変更や問い合わせをしたいと思った時にわざわざ電話をかける手間なく、LINE上で操作できるようになったことは、便利になったのではないかと思います。
ecforce maやecforce biの活用で工数を削減しながら、より効果的な使い方を模索
ーecforce maも導入されていますが使い勝手はいかがでしょうか。
植田:ecforce ma*を活用して、メルマガやLINEの配信を行っています。ecforce ma内で簡単に顧客をセグメントでき、その人数についてもリアルタイムで把握できるところが非常に便利です。LINE配信は送信数に応じて料金が変動するため、事前に送信数を把握できるとコストとのバランスを考慮して最適なお客さまに絞って効率的な配信が行えています。
シナリオ作成についても、画面が直感的でわかりやすく、非常に操作しやすいと感じています。以前のMAツールではシナリオごとに必要な設定を行わなければいけなかったのですが、ecforce maはその必要もなく、こちらで考えたストーリーで自由にシナリオ作成できるので使いやすいです。今後は作成したシナリオごとのデータをもう少し詳細に分析し、高速でPDCAを回していきたいと思っています。

あとは、やはりLINE連携ですね。ecforce maからメールにもLINEにも配信できるというのが便利です。また、使い勝手はもちろんですが、ecforce maを活用してLINEで配信した情報に対するお客さまの反応が良くなったことは、一番の効果です。キャンペーン情報に限らず、保有ポイントやバースデーポイント付与の連絡から購入導線につなげるところの成果が、徐々に上がってきています。特にecforce maの自動ログイン機能を導入してからは、その傾向が強くなっています。パスワード不要でログインできるので、お客さまの反応も良くなった印象です。今後はそういった部分からの売上の向上にも期待しています。
米増:以前のカートシステムは、MAツールを連携できていなかったので、セグメントした顧客情報を抽出したり、都度MAツール側で配信設定をしたりと、かなり労力がかかっていました。ecforce maの導入で、一例ですが、顧客情報の抽出がこれまでの約1/4ほどの作業時間で終えられるようになりました。今は植田一人でこの業務を担えるようになっており、業務効率化が進みましたね。
*ecforce ma:MAツール。簡単で正確なデータ連携が可能、且つ効果的なプリセットを用意。CRM施策の売上効果を可視化し、効率的なマーケティング施策を実行可能とする。
ーecforce biの活用も進んでいるとうかがっていますが、どのように運用されていますか。
米増:以前のカートシステムでは、カスタマイズで各種帳票の出力やデータ抽出を行っていました。カスタマイズしていた分、欲しいデータはすぐに抽出できていたのですが、担当者ごとに必要なデータを私が手動で都度抽出する作業が必要でした。その点、ecforce bi*は、担当者がダッシュボードを見てリアルタイムでデータ分析や資料作成ができると知り、導入を決めました。今はまだ社内でデータの絞り込みの基準や運用が確立できていないため、私が窓口となって担当者のリクエストに合わせたダッシュボードを作成して渡すといった運用にしています。
ecforce biはecforceとシームレスに連携しているので、データの抽出は非常に簡単で時間もかかりません。慣れれば必要な資料をパッと作れるので非常に使いやすく、資料作成にかかっていた工数を大きく削減できました。ただ、ecforce maやecforce biはサービスローンチしてからまだ日が浅いので、今後の開発アップデートに期待したい部分もあります。日々触っていくなかで要望がポツポツ出てきている状態なので、まとまったら開発要望としてお伝えしたいですね。せっかく導入しているので、より効果的に使っていきたいです。
*ecforce bi:データ活用における可視化・分析を行うダッシュボードツール。煩雑なデータ設計や連携等が不要で、EC特有のデータの可視化・分析が容易となる。また、複数のチャネルを跨いだデータの可視化・分析も可能とする。
新たな販売チャネルを模索。データに基づいたブランド運営の実現へ
ー今後の展開について教えてください。
米増:ecforce導入後にポイント制度を開始したので、より使い勝手がよく、魅力的な商品・サービスにしてお客さまに寄り添っていきたいというのは前提にありますが、その上で、オンライン以外の販売チャネルも積極的に検討していけたらと思っています。弊社のブランドの場合、オンラインでの販売がメインで、且つ9割ほどが定期販売という状況ですが、直近では自社ECサイト以外での販売も徐々に増えてきています。ここでecforce biを活用ながら、各販売チャネルのデータを俯瞰で分析し、適切な判断のもとブランド運営を行えるようにしていきたいです。
また、ecforceの導入から一年ほど経過したところですが、ここまではecforceに慣れるための一年でした。今後はより機能を使いこなしながら、事業を大きく成長させていきたいと思っています。
ー最後に、ecforceの導入を検討されている方にメッセージをお願いします。
米増:ecforceは機能のアップデートが頻繁にあり、日々進化しているプロダクトだと思います。外部サービスやツールとの連携も非常に多く、自由度高く選択できるので、カスタマイズも必要ありません。それがecforceの強みといえるのではないでしょうか。 また、ecforceの担当の方も、弊社の課題を解決しようと親身にサポートを行ってくれました。FAQも充実しているため、問い合わせることなく自社内で解決できる部分も多く助かっています。ECシステムの導入に迷っているブランド・企業は、そういう部分も加味しながら検討するといいのではないでしょうか。
植田:特別な知識を多く持ち合わせていなくても、ecforce maでメールやLINE配信などのCRM施策が行えます。シナリオ作成のように専門的な知識が必要なこともFAQを頼りに施策を回すことができるので、導入してよかったと実感する部分です。専門人材でなくとも、短期間で使えるようになるのはecforceの強みであり、事業者側にとっても大きな利点だと思います。
ー本日はありがとうございました。
※掲載内容は取材当時のものです。



